麹(製麹)
1.種切り


蒸米に「種麹」という黄麹菌の胞子をふりかけます。種麹をふりかけた蒸米は「麹室」へと運ばれます。(製麹:1日目の朝)
麹室とは麹造り専用の部屋のこと。温度が約30℃、湿度が約60%に保たれ、温度・湿度を微妙に調節できる機能を持っています。

当社の場合、大吟醸の種切りは麹室で行われます。蒸米を広げて種麹をふりかけます。さらに蒸米を返し、全体に菌が行き渡るようふりかけます。
2.床もみ、もみ上げ


麹菌がふられた蒸米をよく混ぜ込む作業、「床もみ」を行います。床もみ後はひとまとめにして積み上げ(「もみ上げ」)、布を掛けて保温し、8時間ほど置きます。(製麹:1日目の日中)
3.切り返し

8時間ほど経つと蒸米は固まりになっています。これをいったんほぐし、熱を放散させます。そして再びひとまとめにして布をかけておきます。(製麹:1日目の夕方)
翌朝になると黄麹菌の活動が活発になり、温度の上昇が著しくなります。このときに再び切り返しを行います。(製麹:2日目の朝)
4.仲仕事・仕舞仕事


熱を放散させるために米を広げて温度を下げます(「仲仕事」)。さらに熱を放散させるため、米を広げます(「仕舞仕事(しまいしごと)」)。仕舞仕事の後も米の温度はさらに上昇を続け、最高温度に達したときに翌朝までその温度を保持します(写真左)。(製麹:2日目の日中)
翌朝、最高温度を保持した米を乾燥させます。米を台車に移して麹室内の別室に運び、夕方の出麹まで乾燥させます(写真右)。(製麹:3日目の日中)
5.出麹

米から栗のような香ばしい香りがしてきます。そうなると麹ができたサインです。麹室から麹を出します。

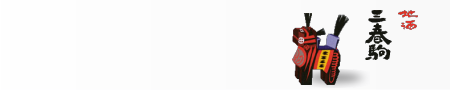
 トップページ
トップページ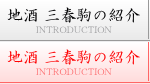 地酒 三春駒の紹介
地酒 三春駒の紹介 周辺環境
周辺環境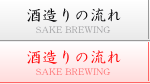 酒造りの流れ
酒造りの流れ 商品情報
商品情報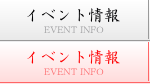 イベント情報
イベント情報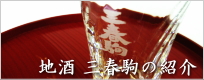 地酒 三春駒の紹介
地酒 三春駒の紹介 商品情報
商品情報 イベント情報
イベント情報